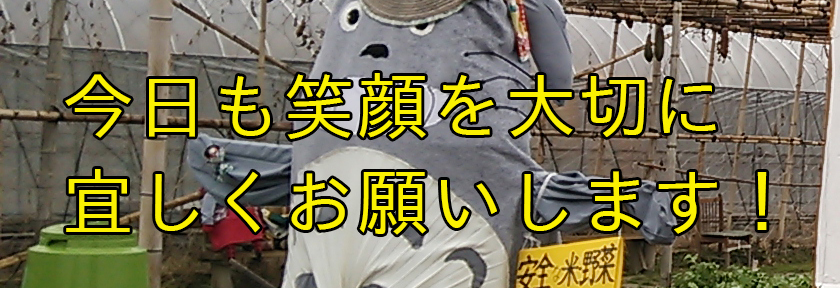私たちが、日常生活上で獲得し続けている「栄養」とは本当に尊いモノです。
私がかつて病院・老人ホームで勤務していた頃、栄養については様々な考え方が当時の現場では飛びあいました。
その意見交換しあった現場の人たちの意識とは、きっと・・・
- 栄養管理を個々の状態(病気・病態・病状等)に準じて適切に実施する事
- 多職種で「食べる事」を支える事
- 人間がどんな状態下にあっても多専門職でサポート出来る事がある
- 絶対に患者さん・利用者を見捨てない意識が重要であり、専門職である「あなた」が最後の砦である
そういった感じの意識なのではないかと思うのです。
では、次に病院とかの現場で警戒している「栄養状態が良くない場合」ってどんな事があるのか?
それは・・・
- アルブミンが下がり全身がむくむ(浮腫)
- 痩せてしまう(体重が減り、筋肉が落ちる)
- 食べ物が飲み込めない
- 手足が拘縮した(動けない、座れない、トイレに行けない状態)
みたいな感じなのだと私は考えています。
※ アルブミンは肝臓で生成されるタンパク物質の事です。血液中を流れるタンパク質の約50~65%を占めており、体を動かす重要な物質です。
しかし、病院で寝たきりの患者さんとかはそれらのSOSを言葉で素直に発信出来ない事が大半です。
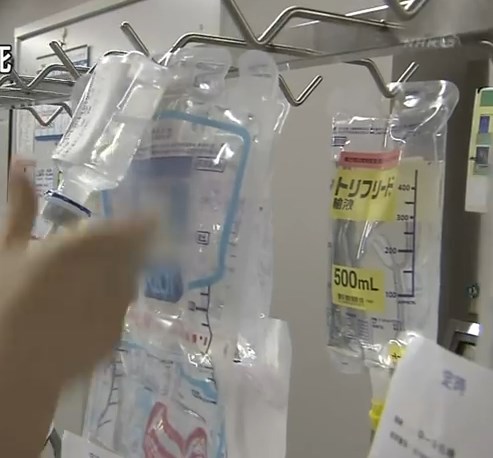
では、その「注意しないといけない信号」とはどんな信号なのか?
- だんだん痩せてしまう
- 筋肉が徐々に落ちてしまう
- 活気(元気)がない、物事への耐久力が低下している
- 浮腫が出てきている
- 皮膚・口腔の粘膜が乾燥してしまう
- よく発熱してしまう
- 下痢、嘔吐、便秘、食欲不振などの消化器症状がなかなか改善しない
軽く見積もっても、これだけの信号は見落とさない事が重要になります。
そうなると、多くの患者さんや利用者を支えていかないといけない病院、福祉施設にてこれらの信号を1職員だけでカバーするには限界があります。多職種で連携して栄養不良が発生した人がいないか注意して観察、ケアを行わないといけません。
まさに、セーフティーネットです!
※ 皆様、貴重なお時間の中、記事をお読みいただきありがとうございます。
もし、記事に共感いただけましたらシェア、もしくは以下の” はてなブックマーク・Twitter・いいね! ”ボタン等を押していただけると凄くうれしいです。
皆様の貴重な応援が、私の更なる元気と勇気につながります。