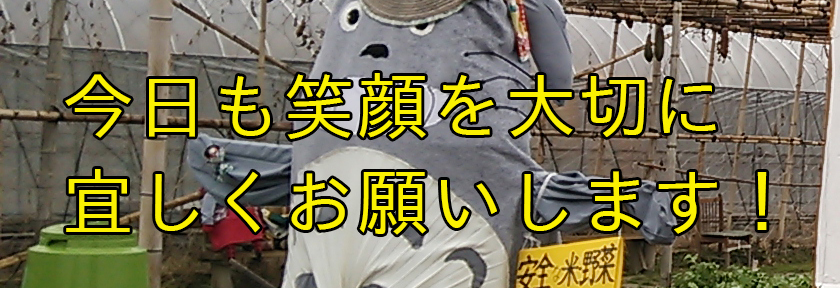以前、自分でかかりつけ医からお薬を貰ったり(医療従事者が管理)する時は5つの確認方法がある事をお話させていただきました。
すなわち
- 正しい患者(right client)
- 正しい量(right dose)
- 正しい時間(right time)
- 正しい薬名(right drug)
- 正しい方法(right route)
以上の手段の頭文字をとって「薬の5R」と呼ばれている方法を以前に紹介させていただきました。
ただ、それに加えてその「5R」を確認するタイミング、つまり、薬を実際に「飲まないといけない本人」が口にするまでに3回はこの5R確認を行うのが「真の内服などの安全確認」と言われています。
その3回とはいつの時か?
それは!
- 薬剤を(未開封状態で)手にした時!
- 薬剤を容器から取り出す時!
- 薬剤の容器(空容器・空袋)を捨てる時!
以上の時期での確認をするのが適切と言われています。
薬は「化学物質」です。飲み方一つで、良い作用にも、逆にもなり兼ねまえん。逆というのは薬がリスク(危険)になるという事です。
特に高齢者の方々は薬の作用が個人差(年齢・遺伝・抱えている病気やその重症度等)激しいです。
なので、薬の管理(コンプライアンス)は大切になってきます。
近年、薬を処方してもらってもそれを飲みきれなくて、薬局に大量返品している事態も発生している悲しい・かつ複雑な問題もよく耳にします。
本当に、医者まかせ・薬剤師・看護師まかせなだけでなく、自分にとっても「この薬は本当に自分に必要な薬なのか?」「これは自分で管理出来る薬なのか?」等の判断を患者さん自身も行う事は大切ではないでしょうか。
そして、もし、自分が薬を管理しきれない時、「何がサポート」するのかの体制も十分備えておく事は「自分の身体」を守り、周囲にも不要な迷惑をかけない事にも繋がってくるのではないでしょうか。
※ 皆様、貴重なお時間の中、記事をお読みいただきありがとうございます。
もし、記事に共感いただけましたらシェア、もしくは以下の” はてなブックマーク・Twitter・いいね! ”ボタン等を押していただけると凄くうれしいです。
皆様の貴重な応援が、私の更なる元気と勇気につながります。