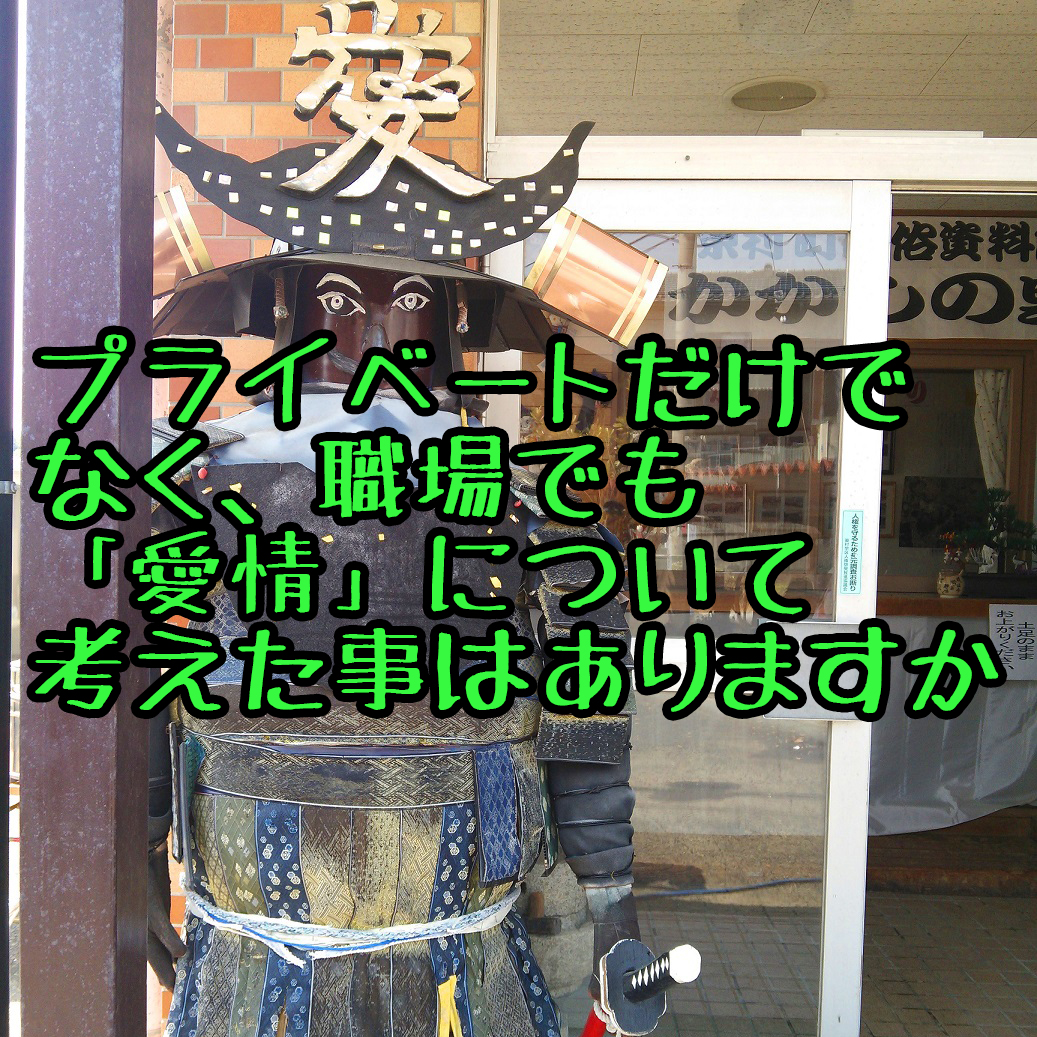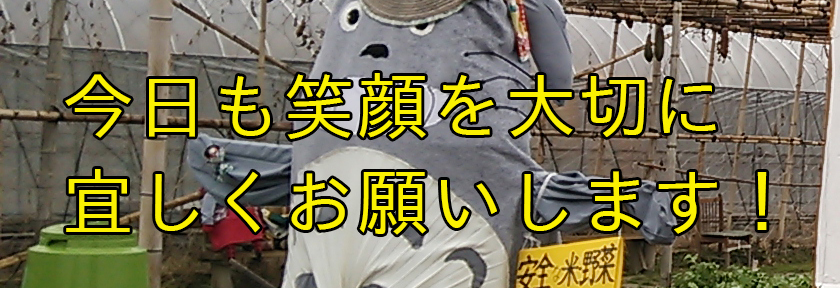看護師国家資格を取り、いや、准看護師時代から病院に勤務していた頃から私にはある「意識し続けていた議題」がありました。
それは、身体拘束という事への考え方でした。
身体拘束とは、厚生労働省より以下10項目の内容であると示されています。
- 歩き回らないようにベットや車椅子に胴や手足をひもなどで縛り、歩けなくする。
- ベットなどから転落しないようにベットに胴や手足をひもなどで縛り、動けなくする。
- ベットの周囲を柵などで完全に囲んだり、高い柵を使用するなどして自分では降りられないようにする。
- 点滴や、鼻やおなかなどにつける栄養補給のチューブなど治療のための器材を自分で抜かないように、手足を縛ってしまう。あるいは皮膚をかきむしらないように、指を思うように動かせなくするミトン型の手袋などを使う。
- 車椅子やいすなどからずり落ちたり、立ち上がったりしないように、Y字型の専用ベルト、腰ベルト(紐)などで車椅子・椅子に縛りつけたり、胴にぴったりと密着するテーブルをつけて立ち上がれないようにしてしまう。
- 立ち上がる能力のある人を、座面を大きく傾かせたりする椅子に座らせるなどして立ち上れないようにする。
- 服を自分で脱いでしまったり、おむつをはずしたりしてしまう人に、介護衣(つなぎ)とよばれるような、自分では脱ぎ着ができない特殊な服を着させる。
- 他の人に迷惑をかけないように、ベットなどに胴や手足をひもなどで縛る。
- 興奮したり、穏やかでなくなったりした人を落ち着かせるために、鎮静させる効果がある精神に作用する薬(向精神薬)を過剰に使って動けないようにしてしまう。
- 鍵をかけるなどして自分では空けられないような部屋に閉じこめる。
以上の項目がその身体拘束に該当するとされています。
身体拘束が良い・いけないという事がポイントではありません!
身体拘束が本当にどこまで「拘束される側にとって必要な事なのか」どうかという事について考えていきたい・・・という事が「私の気にする議題」です。
実際、私が実際病院の現場等でその「身体拘束」を行うところは何度も目の当たりにしてきました。
身体拘束を受けていた人はほぼ全員「高齢者の認知症」の重度の方でした。
とはいえ、身体の苦痛にはきちんと反応を示したり会話もきちんと出来たりされる方も中にはいらっしゃいました。
一方で、例えば初対面の職員に否応なく入れ歯投げつけたり、口の中に入れた食べ物を手に握り投げつけてきたり、分厚い爪でひっかいてきたりする認知症の人も(困難事例の1つとして)・・・。引っかかれた職員は傷まみれと血まみれです。
そのような事例等を踏まえた上で、考えていきたい事・・・。
身体拘束とは何故必要なのか?何故(よほど重大な事態を除き)してはいけないのか?
対応困難な対象者についての事例(上記の”ひっかく認知症のような方”等)があるなら、それはどこまで「その人に合った対応」でその対象者を一人の人間として、職員も接する事が出来るか!
そして、その「現実」から現場側もその対象者のご家族等周辺の方々も目をそらさない事(地域包括との連携なども加味した上で)!
まず、そこが前提条件になると見て、身体拘束の「概念」について考えてみました。
その概念について考え続けて、私が考えついたところは「もし、自分が身体拘束されたらどんな思いがするか?」という点でした。
自分の受けた苦痛が他者に分かってもらえない苦しみ、だけど、自分の意志とは関係なく現場の都合で自分を操作される気分はどんなものか。
私ならおそらく自分が認知症であろうがなかろうが、当然「嫌です」ね。おそらく、誰でも嫌ですね。
身体拘束をせずに医療事故・介護事故を未然に防げるなら、その方法はどんどん現場でディスカッションするべきだと思いますし、全国抑制廃止研究会さんからも同様のご意見を拝見させていただきました。
それをせずに、対象者の苦痛はお構いなしで現場の都合・効率性で物事を判断して行う身体拘束は「暴力」でしかなくなってしまいます。
患者さん・ご利用者さんの事を親身に同目線で観ているのなら、その方々が日常生活上の「苦痛」をどう取り除くのかが必ず優先されるはずではないでしょうか。
身体拘束を行う理由が・・・
- スタッフの数が足りないから?
- 危険行為が激しいから?
- いう事聞かず、クレームばかり言うから?
- 現場がハードになるから?
それはそれ(スタッフの負担軽減)、これはこれ(身体拘束の危険性)で別問題なのではないでしょうか?
それをつい、一緒にしてしまいがちなところを私は凄く恐れています(自分もそういう考え方になってはいけない!と)。
現場を痛い程観て、知っているからこそ、私はそう確信しています。
スタッフの問題と身体拘束の問題は必ず「別」に考えないといけません。
マンパワー(スタッフの人財不足)の限界は、アイデアと職務の「強み」で解決するしかないのかもしれません。
絞って出るところから出す(絞っても出ないところに依存しては時間も労力も信頼も壊れる・・・)のが今の最善策な気がします。
そこが曇るととんでもない事故や危険概念(様々な暴力等)を生み出してしまうのではないでしょうか。
あと、近年、介護ロボットというモノ(新企画)が徐々に誕生・更に多くの施設へ普及する方向性が検討(既に実践されてる施設さんも)されています。
その「介護ロボット」も元は「身体拘束STOP」と「介護が必要なお年寄りの安心した生活のサポート」が原点(役割)のはずです。
その中で、スタッフも心が折れる事無く今後どう充実した介護に努められるか!
その考え方が大切だという事を今一度再認識すべきなのかもしれません。
そして、私自身も今後「身体拘束の課題」についてはまだまだ未知・無知な部分も多いので、今後も勉強していきたいと思います。
自分が介護予防運動を実践する目的も「身体拘束・寝たきりのような危険から高齢者を守りたい事」、そして「介護が必要なお年寄りの安心した生活のサポート」にあると意識しています。
だからこそ、高齢者が多く集まりやすいデイサービスやコミュニティなど、様々な場所に足を運ばせてもらっています(から)。
※ 介護ロボットの件については後日触れていきたいと思います。
(引用・参考文献)特定非営利活動法人「全国抑制廃止研究会」様より
※ 皆様、貴重なお時間の中、記事をお読みいただきありがとうございます。
もし、記事に共感いただけましたらシェア、もしくは以下の” はてなブックマーク・Twitter・いいね! ”ボタン等を押していただけると凄くうれしいです。
皆様の貴重な応援が、私の更なる元気と勇気につながります。