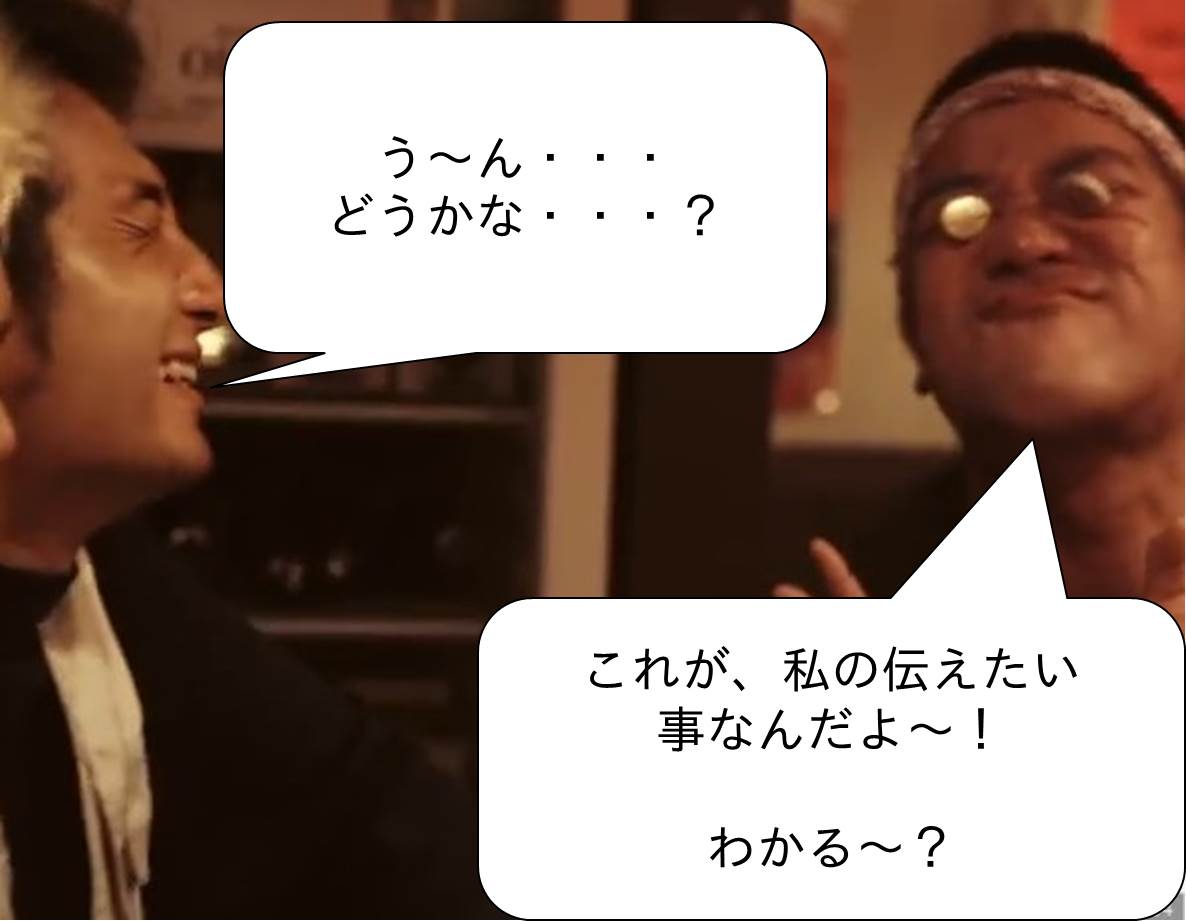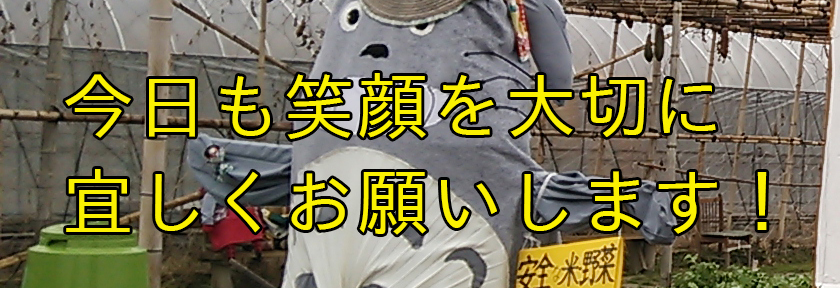私も最近、地域関連・ボランティア関連の会合や職場の話し合い等、いずれ「介護予防運動」に関連した場に出る事が多々あります。
会合もとい介護の内容が「介護予防運動」に直接関係するか、間接的に関係するか、それだけの違いなだけで私にとって「会議」は重要な存在です。
そんな、ありがたい「機会」の中で特に私が感じる事があります。
それは、会議に参加している人達には2通りのタイプの方がいるという事でした。
自分・もしくは他者の意見にプラス思考に反応される方と、マイナス思考に反応される方!
もっと分かりやすく述べますと
- 「未来にうまく繋がる発言をされる方」
- 「未来のない自分中心・もしくは会議自体に意欲を示さない方」
その2通りのタイプの人達に分かれるのが、真剣な会議程あからさまに分かってしまいます。
以前、別の記事で「話の聴き手の条件」と「話をする側の条件」についての議題には触れてみたと思います。
そして、今回はそういったモノもひっくるめた「会議」とか「集会」というモノで確実に認識しておきたい4つの条件について触れてみたいと思います。
では、その「未来に繋がる会議が出来る」最低限必要な4つの条件とは!
- 「批判をしない事(意見に同調したところからの発言)」:他人の意見を批判してしまうと、良いアイディアが出にくいので話題を肯定的に繋げて進めていく事(「そういう考え方もありますよね~」とか「確かにそうですね~」といった反応が大切)。
- 「自由奔放(意見を述べる事は恥ではない!という考え方)」:自分の意見で笑われたりしないか、とか意識せずに、ひらめいた考えをどんどん言っていく。ジョークなど「場を盛り上げる話し方」もありです。
- 「質より量(サンプリング)」:出来る限り、多くのアイディアを出していく事が必要。後にそれらをジャンル別に整理したり出来て便利!
- 「連想と結合(他者の意見をヒントにする、または進化させる)」:他の方々の意見をまず、聞く。そしてそれに反応し連想を働かせる。もしくは他者の提案に自分のアイデアを加えてみて、新しい意見として発言する。
以上の内容です。
と、これ・・・どこかで聞いた事あるような・・・と思われる方もいらっしゃると思います。
そう、これは「ブレーンストーミング」もしくは「kJ法」と呼ばれる会議手法での大切な4つのルール項目の事です。
必ずしも、全てが全てこのルールに当てはめないといけないとは思っていないです。
ただ、会議の中に否定的・マイナス因子(中傷・批判言語)が入ると、その弁解を互いにやり合ってしまいます。
そうなると、本来解決案を整理・導き出したかった「本来の議題」から話が遠ざかってしまい、その弁解だけで会議が終了してしまいます。
もともと「ブレーンストーミング」や「KJ法」もこういった危険を防ぐ為に導き出された会議手法なのです。
その「危険」とは「会議の本来の主旨から話題がズレてしまう事でせっかく集まった方々の貴重な時間を破壊してしまう事」です。
会議とは「時間」を非常に浪費します。その「時間」とは本来仕事とか育児とか息抜きとかで使われるはずのモノです。
時間はどの人間にとっても「タイム・イズ・ライフ(時間は命と同じ)」です。
だから、人と約束とかしている時は基本、理由連絡のない「遅刻」は最悪です。
「遅刻は社会人としても命取り」と言われている位、時間の約束事の厳守は基本的に大切です。
という時間の重要性は「会議」等にもやはり当てはまる・・・私はそう考えています。
私自身も含め、今までだけでなく今後も気を付けていきたい事だと認識しています。
そして会議の最後あたりくらいは「笑顔」で締めくくりたいとも思ったのですが、どうでしょうか!
※ 皆様、貴重なお時間の中、記事をお読みいただきありがとうございます。
もし、記事に共感いただけましたらシェア、もしくは以下の” はてなブックマーク・Twitter・いいね! ”ボタン等を押していただけると凄くうれしいです。
皆様の貴重な応援が、私の更なる元気と勇気につながります。