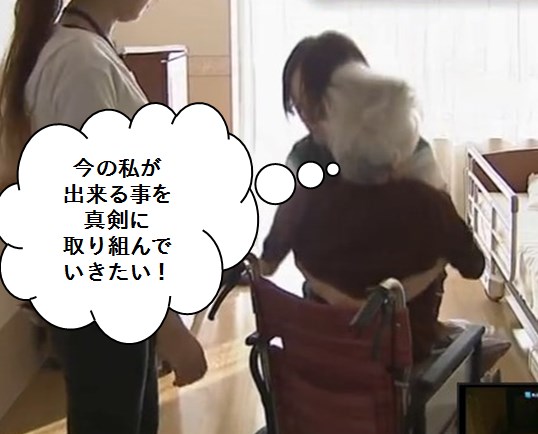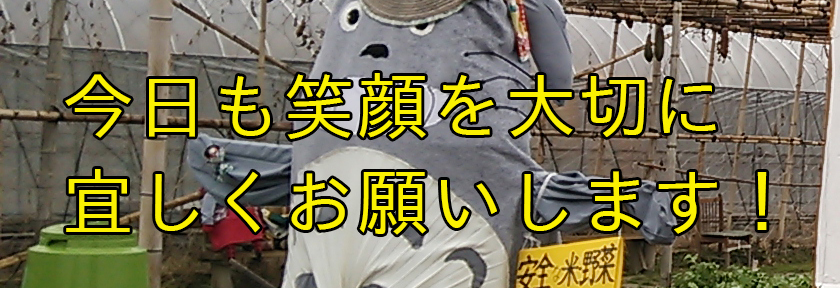以前、ブログで2005年に介護保険法改正が行われ、起動された「地域包括支援センター」について少しお話させていただきました。
そして、その地域包括支援センターとは自分達市民の住んでいる地域で高齢者やその家族が安心して暮らせる為の介護・保健・福祉などでの「暮らしに関しての相談」の窓口である事も少し触れてみました。
その地域包括支援センターは市町村ごとにその相談窓口を設置指定しています。
ただ、一言で「相談(自宅・地域訪問とかでの)」と言っても、実はその地域包括支援センターも地域ごとに活動している幅は膨大(数人の相談職員が、数百・数千単位の市民の相談受け持ちしているというレベル)です。
その代表として以下の規定があります(少し難しい内容かもしれませんが、すいません)。
包括的支援事業の内訳(介護保険法第115条の44より)
包括的支援事業は、以下の4つの事業で構成!
- (介護予防ケアマネジメント事業)二次予防事業の対象者(主として要介護状態等となるおそれの高い状態にあると認められる65歳以上の者)が要介護状態等になるのを予防する為、その心身の状況等に応じて、対象者自らの選択に基づき、介護予防事業その他の適切な事業が包括的かつ効率的に実施されるよう必要な援助を行うもの。
- (総合相談・支援事業)地域の高齢者が、住み慣れた地域で安心してその人らしい生活を継続していくことが出来るようにする為、どのような支援が必要かを把握し、地域における適切なサービス、関係機関および制度の利用に繋げる等の支援を行うもの。業務内容としては、総合相談、地域包括支援ネットワーク構築、実態把握など。
- (権利擁護事業)権利侵害を受けている、または受ける可能性が高いと考えられる高齢者が、地域で安心して尊厳のある生活を行うことが出来るよう、権利侵害の予防や対応を専門的に行うもの。事業内容としては、高齢者虐待の防止および対応、消費者被害の防止および対応、判断能力を欠く状況にある人への支援など。
- (包括的・継続的ケアマネジメント支援事業)包括的・継続的ケアマネジメント支援事業は、地域の高齢者が住み慣れた地域で暮らす事が出来るよう、個々の高齢者の状況や変化に応じた包括的・継続的なケアマネジメントを介護支援専門員が実践することが出来るように地域の基盤を整えると共に個々の介護支援専門員へのサポートを行う。
(介護保険法第115条の46第6項)
地域包括支援センターの設置者は、包括的支援事業の効果的な実施のために、介護サービス事業者、医療機関、民生委員法 (昭和二十三年法律第百九十八号)に定める民生委員、高齢者の日常生活の支援に関する活動に携わるボランティアその他の関係者との連携に努めなければならない。
以上の内容がざっと地域包括支援センターの方々の活動内容の「介護保険法的基盤」となっています。
ただ、それでも上記の言い回しでは「難しく感じる」と思うので、更に砕いた表現で述べたいと思います。
地域包括支援センターの包括的支援事業4つは簡単に述べますと
- 高齢者の方々で支援が必要とする(ように認定された)人への介護保険の予防計画を作成したり、その実施のサポートをする事!
- 地域と協力して虐待予防・認知症による財産管理困難などのサポートを行う事!
- 高齢者の方々やその家族の、もしくは近隣にお住まいの人の暮らし・介護に関する悩み・問題等も対応する事!
- 地域を支えているケアマネージャー(介護支援専門員)との支援、その他高齢者の方々にとって安心して生活しやすい地域にしていく為、様々な機関との連携(ネットワーク形成)に尽力していく事!
これら4つが簡略的に述べた「地域包括支援センター」の方々の業務です。
ただ、ここで私達相談者(地域住民)がいくつか注意しておかなければならない事があります。
ただ、その件は次回にお話ししていきたいと思います!
※ 皆様、貴重なお時間の中、記事をお読みいただきありがとうございます。
もし、記事に共感いただけましたらシェア、もしくは以下の” はてなブックマーク・Twitter・いいね! ”ボタン等を押していただけると凄くうれしいです。
皆様の貴重な応援が、私の更なる元気と勇気につながります。