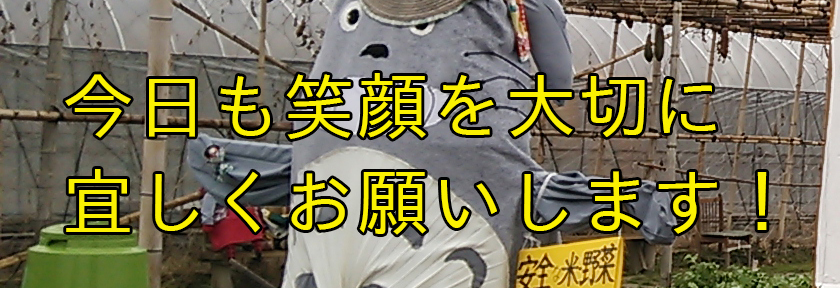以前、地域包括支援センターの役職とは主にどんな事があるかについて触れていきました。
そして、今回お話していきたい事とは・・・
地域包括支援センターに相談しつつ、自分や自分達の家族を守る私達相談者(地域住民)がいくつか注意しておかなければならない事があります。
まず、あくまで地域包括支援センターが介護系や虐待予防などで相談できる機関であるとしても、その解決の鍵を握る主役はあくまでも当事者である「高齢者とその家族」です。
そういった主役の立場を忘れた住民が無鉄砲に地域包括支援センターを利用した(利用せざるを得ない事態な)際、大変な危険(相談件数に応じきれない・もしくは介護者続出・町の衰退、廃村)に繋がりかねません。
地域包括支援センターを利用する際に住民が必ず忘れてはならないのは
- 個人が利益・市場独占の為だけに地域包括支援センターを利用しない事(大企業ばかりが中小企業の市場・営利を独占しない事)!
- 介護・少子高齢化・地域の問題は自分達一般市民(地域住民)側でも解決に取り組むべき問題でもある事を忘れない!
- 市・包括センター・地方自治体・企業・市民・学術機関の連携が各地域ごとできちんととれている事!
- 中年・高齢者の方々自体が「認知症予防(緩和)や介護予防を行う事は、息子・孫の世代に多大な迷惑をかけない事」であるという事を絶対に忘れてはいけない事!
- (上記と並行して)介護予防運動や健康への自己管理の意識などを高齢者・中年世代の方々が心掛ける事は家庭の不協和音の回避にもなる。それが間接的に「学校のいじめ・校内暴力・夜間の若者徘徊の防止」にも繋がるという実態も認知しておく事!
こういった「地域現場」の事実・現状は本当に「地域創生のルール」と大きく関係してくるので忘れてはならない事だと思います。
それを軽んじるという事は、どこかの他人が空き缶を不法投棄(道端に投げ捨て)したら、代わりに誰かが拾わないといけないというのと同じ事だと私は考えています。自分の不手際を人任せにする(問題への無関心)は罪です。
(注) 私は別に地域包括支援センターの職員ではありません。ゆえに、各住民の役職・学問的立場を理解しておく事は大切です。その上で、どこまで「個人・地域での連携による地域ケア(創生)への力を注ぐ(協力し合う)事が出来るか」を住民一人一人が知っておく事が大切ではないかと述べておきたかったのです。
全ての介護上・家庭上の問題を「市や包括に任せときゃいいんじゃ!そんな事は!」になってはその地域の治安はメチャクチャです。
それでは各立場の役職者・住民共々モチベーションも低下し、その地域は明らかに衰退していきます。だからこそ、本来各地域に備わっていたはずの「地域力・人間力・家族の助け合い・絆」の見せどころではないでしょうか。地元住民が地域の為に全く何も活動が出来ないはずは絶対にないと思います!
必ず何か小さな事でも出来る事はあるはずなのではないでしょうか。
※ 皆様、貴重なお時間の中、記事をお読みいただきありがとうございます。
もし、記事に共感いただけましたらシェア、もしくは以下の” はてなブックマーク・Twitter・いいね! ”ボタン等を押していただけると凄くうれしいです。
皆様の貴重な応援が、私の更なる元気と勇気につながります。