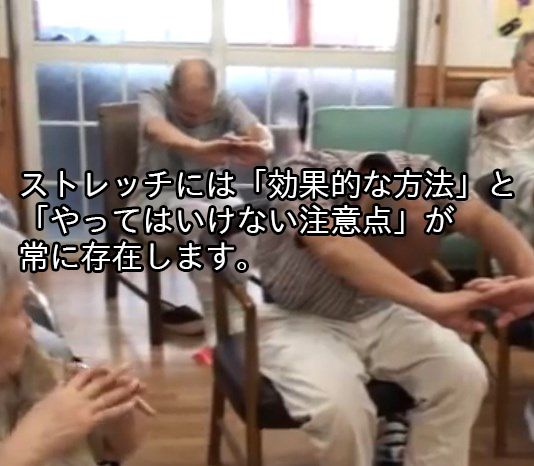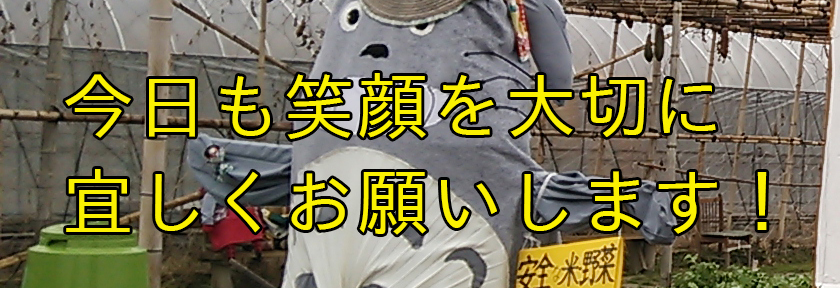看護師などでデイサービス・デイケア施設とかで働いてらっしゃる方、福祉施設・病院等でリハビリテーションで活動されているリハビリ専門職者の方々の立場について今回考えてみました。
病院で手術・脳梗塞・関節リウマチ等といった状態が起こった後、もしくは福祉施設で普段筋肉が衰えている方、もしくは衰えないように注意しないといけない方々(介護保険法で言う要介護者・要支援者の方々)へのサポートで代表的なのは「身体の柔軟運動・筋力アップ」の体操です。
体操自体は、その行う趣旨が病院のリハビリと福祉施設の介護予防運動(施設内で言う個別機能訓練加算・運動器加算等)で違いはいくつかありますが、100%共通している事が1つあります。
それは・・・・寝たきり(廃用症候群による最期)を予防する事です。
なので、リハビリの職員の方も介護予防運動を実施されている職員の方も「その点に共通した注意点」が存在します。
その「寝たきり予防体操について注意していきたい4つの注意点」とは、以下の症状の進行の観察・緩和・予防です。
- 失認・・・5段階ほどの種類(視覚失認や色彩失認等)意識障害などはないはずなのに理解したいモノの意味・価値観などが認識できなくなる状態の事。
- 失行・・・これも5段階ほどの種類(観念運動失行や着衣失行等)に分かれています。どれも共通しているのは認知症や全身の麻痺とかが生じていないのに運動・動作を意識(随意的)して行えない状態にある事。
- 構音障害・・・口唇や舌、喉などが備わっているべき発語に必要な構音器官がうまく働いてくれない・口の中の筋肉とかがいう事を効かない状態。そして、その状態の為に発音に障害を来す事。
- 失語症・・・脳の病気による後遺症とかがきっかけで言語中枢(左大脳に9割方ある機能)に問題が発生する。その発生する状態とは「聞く力」「会話する力」「文章を読んだり書いたりする力」が障害されてしまう事。
これらの障害の主体的な発症源は「脳」にあります。しかしながら、それを助長してしまうのは、やはり「寝たきり状態による全身機能の低下」、そう「廃用症候群」という状態です。
私も今まで何人も廃用症候群で最期を迎えたり、望んでもないのに苦しい処置を受けざるを得ない状態になった患者さん・施設ご利用者さんを沢山お見受けしました。
もう、そういう人が増えないように・・・・・
そして、高齢者の方々もご家族と共倒れになるような道を歩まないように・・・・・
これ以上、介護負担の重責が未来の若者に委託されないように・・・・
今、私も含め、病院・施設外の一般市民、市、また、それを支える政治機関の方々にも、その壁をどう乗り越えるかの「課題」が求められているのではないでしょうか。
※ 皆様、貴重なお時間の中、記事をお読みいただきありがとうございます。
もし、記事に共感いただけましたらシェア、もしくは以下の” はてなブックマーク・Twitter・いいね! ”ボタン等を押していただけると凄くうれしいです。
皆様の貴重な応援が、私の更なる元気と勇気につながります。