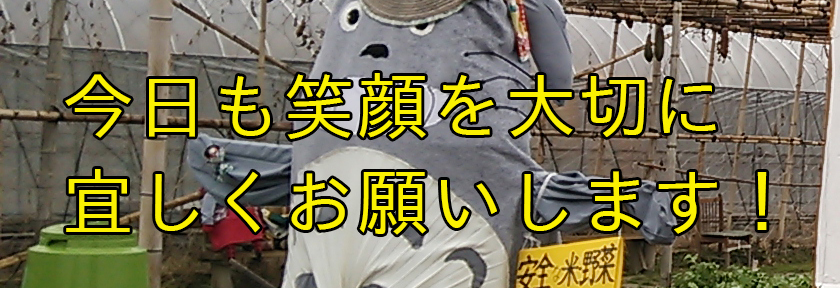私は現在、いち看護師として様々な場で高齢者の方々の介護予防運動に関わってきました。
そして、時には私自身が介護予防運動を実施してきた事も何度かありました。
最近関わってきたのは福山市~尾道市内のデイサービス・地域包括支援センターでした。
その際に私が以前ブログで述べた事がありました。
それは・・・
最低以下3つの注意点にこだわり、介護予防運動を尾道市~福山市内で行っている・・・という事です。
その介護予防運動時気を付けている三つの注意点とは!
- 参加者(高齢者)の立場・心身の状態を考え、無理はしない。
- 体操は必ず1クール30分未満が限度。
- 体操の最初・途中・最後は必ず腹式呼吸による深呼吸を適用する。
これは、どの現場においても私は基本的に方針は変えていません。
で、今回は1番目に述べた「参加者の立場・心身の状態を意識し無理しない体操」についてお話出来たらと思います。
無理しないという事は介護予防運動を行う現場に置いては全てにおいて当然の事です。
ただ、どう無理しないのか例を挙げてみます。
例えば「ペースメーカー挿入者」や「肩の粉砕骨折の手術経験者等」の方の場合です。
そういった方々に「朝のラジオ体操」と同じような「手を上に上げて~」とかいう体操を勧めてしまうとどうなるでしょうか?
まず・・・
ペースメーカー挿入の方は胸の筋肉(大胸筋)が絡む部分付近に電極のリード線が埋め込まれています。
そんな状態で胸の筋肉を伸ばす運動をしてしまうと・・・・ペースメーカーと心臓とを繋いでいるリード線が切れる危険性があります。
次に・・・
肩の粉砕骨折・もしくは関節リウマチや骨粗鬆症(骨軟化症)のひどい方が肩を上に上下する体操をしたら・・・せっかく修復した創部が悪化(再骨折・出血・炎症化)してしまいます。
そんな風に、心身の状態や病歴の内容によっては勧めてはいけない体操もあります。
なので、介護予防運動を実施する指導者はその「配慮」も注意しなければなりません。
また、これは私が「ボランティアの現場等」で拝見したモノですが・・・
ご自分の身体の状況をうまく表現出来ない(認知症・もしくは性格上のケースなどで)お年寄りもいらっしゃいます。
そういう方もいらっしゃり、そういう現場で介護予防運動(ボランティアなどで)しないといけない場合は・・・
ケースバイケースもありますが、基本お年寄りの表情・しぐさ等注意しながらこちらからインテークする(積極的に尋ねないといけない)事もあります。
そういう意味でも介護予防運動とは、ただ「人を集め体操さえ教えていればいい」というモノでは決してない!という事になります。
※ 皆様、貴重なお時間の中、記事をお読みいただきありがとうございます。
もし、記事に共感いただけましたらシェア、もしくは以下の” はてなブックマーク・Twitter・いいね! ”ボタン等を押していただけると凄くうれしいです。
皆様の貴重な応援が、私の更なる元気と勇気につながります。