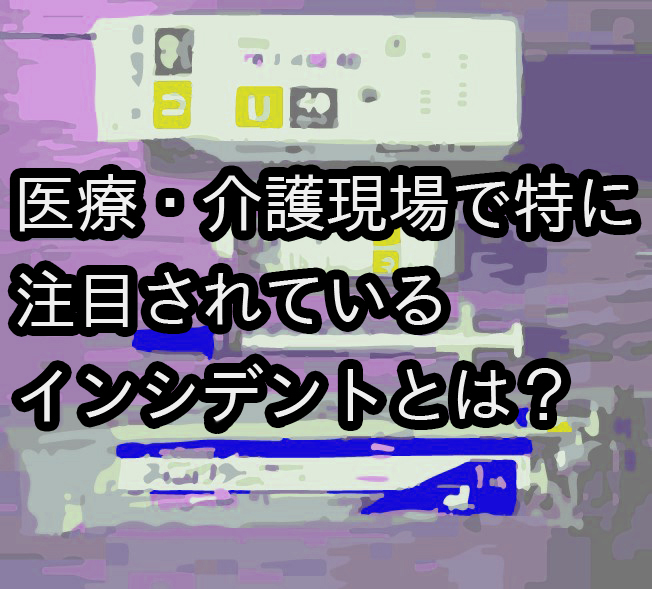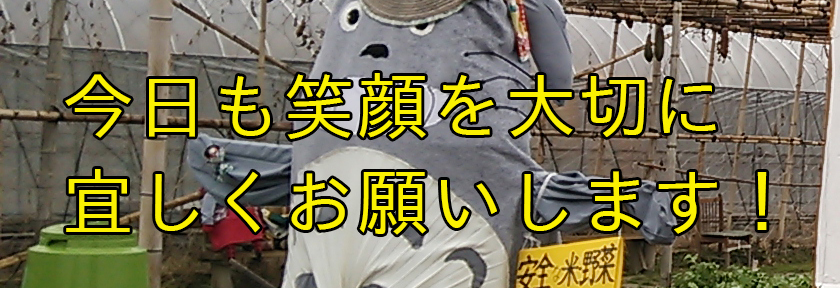皆様、貴重なお時間の中私の記事を見て下さり、本当にありがとうございます。
今回は介護予防と少し視点を放して医療や福祉の現場のインシデント(問題・自己につながり兼ねない事例)について解説してみたいと思います。
ちなみに一方、アクシデントという言葉もありますが、これは「事故」「問題発生」を意味します。
その前に一つお断りさせていただきたいのは、この記事の主旨は絶対に「ミスをしている人を批判する事」ではありません。
「人の失敗を他人事のように捕えず、だれもが陥りやすい危険性をチームの間で情報交換する事でその困難に立ち向かい解決する!」。その事の大切さについて書いた記事です。
また、かつて私がそれで幾度となく失敗し沢山泣いた事もあった(未だに考えさせられる)のも、この議題を取り上げた理由の一つです。
では、まず結論から言いたいと思います。
私の知る限り、様々な大学病院の情報や論文など、そして、私自身医療や福祉の現場を体験して、一番よく遭遇したインシデントミスは「糖尿病治療薬、インシュリンの投薬忘れ、投薬ミス」でした(ただ、医療行為の少ない介護施設は、転倒というインシデントの方が多いようです)
ちなみに少し簡潔に糖尿病について説明します。
糖尿病とは、膵臓から分泌されるインシュリンが少ないか、高脂血症などが原因でカロリー過多になり、体内に必要以上に糖分や脂肪がたまり、それらが体内で栄養として活性化出来ない(高血糖状態な)病気です。
悪化し高血糖状態が長期間続くと、
- 腎機能障害(透析のお世話になったり)
- 網膜症(視力低下・失明など)
- 神経障害(足などの末梢神経・血管の壊死・下肢の切断)
等の危険性があるとされています。逆に低血糖状態が続くと、脳や筋肉(心臓の心筋も含む)などに糖分が届かず、命に関わる事があります。
通常は糖尿病に対し「食事療法」「運動療法」で血糖値をコントロールするわけですが、病状が進んでいるケースの場合、そこに加え「薬物療法」が適用されます。
その、血糖のコントロールに使われる薬は「ブドウ糖補給」とか、食前の「血糖低下薬」か「インシュリン」とかがあるのです。
で、実際・・・医療分野のインシデント件数・種類の公開(大学病院などの学会レポートなど)をネットや文献で検索した際の結果表示や、自分が過去に直に医療・福祉現場に携わった結果から見ても、やはりこの「血糖コントロール」でのインシデントが際立って多く検索結果としてひっかかったです。
あと、そこに加えて、私はある大学病院の論文らしき一説でこのような事を拝見した事がありました。そこには(私の箇条書きですが)以下の感じの内容が発表されていました。
- (第一に)インスリン治療は, 指示の多様性や注射指示から実施までのプロセスの複雑さ等で, インシデントにつながる事が少なくありません。
- (第二に)医師, 看護師の安全対策チームを結成し, インスリン治療の標準化を実施しました。
- (第三に)だが, その後もインスリン注射インシデントは発生しました。
- (第四に)その原因の一つに, (医師が処方指示し看護師が使用する)インスリン指示書に係る問題があると考えられました。
- (第五に)そこで医師の指示記載部分の簡略化と患者情報共有化に重点をおきました。
- (第六に)そしてインスリン指示書を改良し, その効果を見て、インシデントの発生件数とその内容を再評価しました。
- (第七に)インシデントの発生数は,変わらなかったがインシデント内容を見ると, 投与速度間違いや投与日時間違いといったインシデントが, 減少しました。
- (第八に)しかし, 「注射し忘れ」の件数は変わらず今後の課題です!
簡略化したら以上の内容です。インシュリン等のミス防止で大学病院等の医療チームが以上のように幅広く動いています。
では、何故それでも現在なお病院や介護施設で「インシュリンの時間通りの投薬忘れ」のミスがおこる(おこりやすい)のでしょうか。
次回はそのミスの真意を考えて記事を書いていきたいと思います。
※ 皆様、貴重なお時間の中、記事をお読みいただきありがとうございます。
もし、記事に共感いただけましたらシェア、もしくは以下の” はてなブックマーク・Twitter・いいね! ”ボタン等を押していただけると凄くうれしいです。
皆様の貴重な応援が、私の更なる元気と勇気につながります。