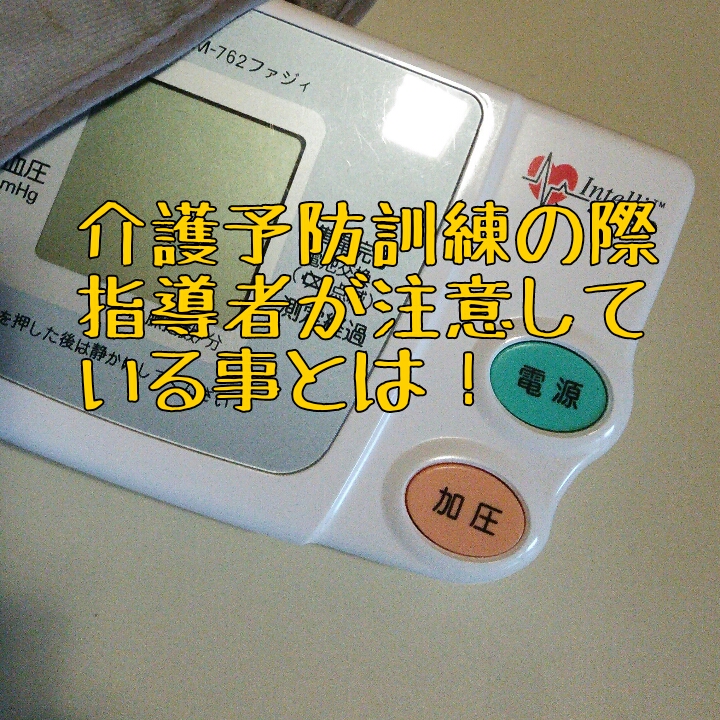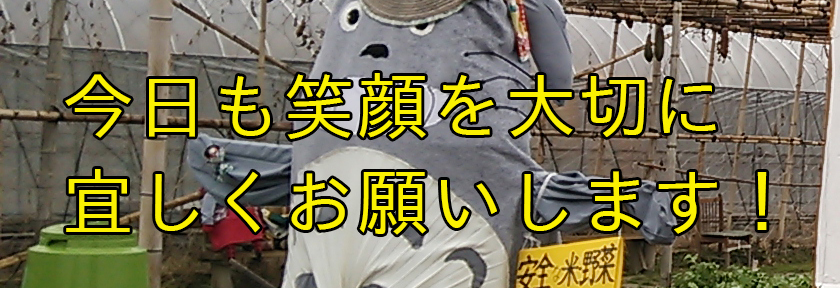高齢者が寝たきりを防ぐ為に、そして何より転倒を防ぐ為に私も福祉の現場で実施している「介護予防訓練」!
しかし、そういった訓練を実施している高齢者もいれば、訓練を拒否される人も・・・。
(特に訓練とかされずに引きこもりな方々の場合に)施設入所者や病院の患者さん(高齢者の)が誤って転倒し骨折!
そのようなケースも未だ後を絶たない現状である現在!
では、その「骨折」の要因はどういった場合に起こりやすいのか?
私は高齢者の方々特有のある症状を主に意識しています。
それは、骨がもろくなる事です。
ここで・・・・なぜ私が骨がもろくなる事を単純に「骨粗鬆症(こつそしょうしょう)」と表現しなかったか?
それは、今一度骨がもろくなる病気をきちんと区別しておきたいからです。
まず、加齢等で骨がもろくなる代表的なものとして「骨粗鬆症」と「骨軟化症(こつなんかしょう)」という2種類があります。
では、その2つの違いとは・・・
- 骨粗鬆症とは骨の容積は減るが、血液中のCa(カルシウム)・P(リン)・ALP(アルカリフォスファターゼ)といった骨に関連する栄養・酵素は変化していない!すなわち正常値である事がメインである!
- 骨軟化症とは骨の容積は変わらないが、血液中のCa(カルシウム)・P(リン)は減り、ALP(アルカリフォスファターゼ)は増加している!
以上のような大きな違いがあるそうです。
しかし、意外と「骨粗鬆症って骨の中のカルシウムとか減るんでしょ!」という意見を昔からよくお年寄りから伺います。
つまり、骨粗鬆症と骨軟化症を混合して考えてらっしゃる方が多いようです。実は私も昔はそう混合して考えていました(すいません!!)。
なので、自分が例えば「足や手の関節を伸ばし曲げすると痛い!」時、それが例えば骨粗鬆症傾向によるものか、骨軟化症傾向によるものか!
その原因によって身体の管理上の注意点は大きく分かれてきます。
では、次回で「骨粗鬆症」「骨軟化症」ともに共通した注意点についてお話出来たらと思います。
※ 皆様、貴重なお時間の中、記事をお読みいただきありがとうございます。
もし、記事に共感いただけましたらシェア、もしくは以下の” はてなブックマーク・Twitter・いいね! ”ボタン等を押していただけると凄くうれしいです。
皆様の貴重な応援が、私の更なる元気と勇気につながります。